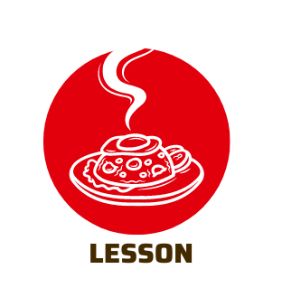「薬膳の資格は意味がない?」と検索しているあなた、薬膳に関する資格取得に興味があるものの、本当に役立つのか疑問に思っているのではないでしょうか?薬膳は健康や美容のために効果的とされていますが、その資格がどれほどの価値を持つのか気になるところです。本記事では、薬膳の資格、特に薬膳マイスターと薬膳コーディネーターの違いや、その資格がどのように役立つのかを詳しく解説します。薬膳資格の取得を検討している方にとって、疑問を解消し、実際に資格取得が意味ないのかどうかを判断する手助けとなる情報を提供します。
ポイント
- 知恵袋の評価
- 薬膳の資格はどれが最適か
- 薬膳マイスターと薬膳アドバイザーの違い
目次
薬膳の資格は意味ない?
- yahoo知恵袋の口コミ
- 薬膳の資格いらないのか?
yahoo知恵袋の口コミ
質問
お尋ねします。
薬膳の国際資格を取った場合、どんなメリットがあるのでしょう?
ベストアンサー
国際資格という事は民間資格に過ぎないわけです。
つまり名乗ることができるだけで、独占業務もないです。
世の中の9割以上の民間資格は資格商法ですから。
なので、自己研鑽とかですね。あとは資格マニアかな。
質問
薬膳コーディネーターという資格はユーキャンを通さないと取れないのですか?
そもそも一般的に認められている(?)資格なのですか?ユーキャンが作り出したものですか?
その他にユーキャンを通さないと行けない資格などはありますか??ベストアンサー
そういった民間資格は、そもそも講座受講料を目的としているので基本的には独学じゃ無理です。
講座受講料と受験料をセットにしています。
誰でもお金さえ払えば短期で100%合格できます。そして、「合格証のようなモノ」がもらえます。
けれど、所詮民間の検定試験なので合格しても就職や転職は有利になりませんし、履歴書に書いてもスルーです。
単なるお金と時間の無駄遣いにすぎないということです。
つまり、資格商法なんです。
広く浅く多くの人から5万円程度のお金を集めるやり方を「現代版資格商法」といいます。
ユーキャン、キャリカレ、諒アーキテクトラーニング・・・全て講座受講料と受験料をセットにした資格商法が主流です。
薬膳の資格いらないのか?
薬膳の資格が本当に意味があるのか、疑問に思っている方も多いかもしれません。この記事では、薬膳の資格について、その意義や活用方法を分かりやすく解説します。
資格を生かすかどうかはあなたしだい
薬膳の資格が意味がないと感じる人もいますが、これは資格の使い方や目的次第です。資格を取るだけでは、直接的に仕事に結びつかない場合もあります。そのため、資格をどう活かすかが重要です。
例えば、薬膳の資格を持っているからといって、それだけで職が得られるわけではありません。資格を活かすためには、さらに応用力や実践力が求められます。国家資格である管理栄養士や調理師と比べて、薬膳の資格は民間資格なので、就職の際に直接的な強みとはならないことも多いです。
しかし、薬膳の資格は個人の健康改善に非常に役立ちます。例えば、「むくみが取れない」「頭が重い」「腹痛がある」といった不調を改善するための知識を学べます。薬膳の講座を選ぶ際には、論理的に教えてくれる講座を選ぶことが大切です。
薬膳の資格を取るならどれがいいか
薬膳の資格を取る際には、自分の目的に合った資格を選ぶことが重要です。たとえば、むくみを改善したい場合には、実際にむくみを改善した実績のある講座を選びましょう。また、カフェ開業や料理教室の開業を目指している場合は、実際に開業している人がいる講座を選ぶと良いです。
後ほどどの資格がいいのか詳細を述べるので、知りたい方は下にスクロールしてください。
薬膳の資格の活かし方
薬膳の資格を最も活かせる方法は、独立して自分でビジネスを始めることです。薬膳カフェの開業や薬膳料理教室の運営など、自分の知識を直接的に活かせる場を作ることができます。
また、薬膳の知識は自身や周囲の人の健康管理にも役立ちます。日常の食生活に薬膳の知識を取り入れることで、体質改善や健康維持が可能になります。
科学的根拠のある和食で体質改善ができる資格講座
薬膳と同様に、科学的根拠に基づいた和食の知識を学べる「和食ライフスタイリスト」という資格講座もあります。この講座では、東洋医学と西洋医学の両方の知識を取り入れた健康的な食生活を学ぶことができます。
受講生は、食生活を少し変えるだけで、便秘や貧血の改善などの健康効果を実感しています。このような講座を受講することで、薬膳の知識とともに幅広い健康知識を得ることができます。
まとめ
薬膳の資格は、目的に合わせて正しく活用することで大いに意味があります。個人の健康改善やビジネスとしての活用方法は多岐にわたります。また、科学的根拠に基づいた資格講座を選ぶことで、より効果的に薬膳の知識を活かすことができます。
薬膳の資格を取得することは、単なる知識の習得にとどまらず、健康的な生活を実現するための大きな一歩となるでしょう。自分の目的に合った資格を見つけ、ぜひ挑戦してみてください。
薬膳の資格は意味ない?の補足事項
- 薬膳の資格はどれがいい?
- 漢方アドバイザーは何ができる?
- 薬膳マイスターと薬膳アドバイザーの違いは?
- 国際薬膳師について
- 薬膳漢方検定は難しい?
- 薬膳の資格は意味ない?まとめ
薬膳の資格はどれがいい?
薬膳の資格を取得したいと考える人が増えていますが、種類が多すぎてどれを選べばいいのか悩むことも多いでしょう。そこで、今回は薬膳の資格をいくつかのカテゴリーに分け、それぞれの特徴やおすすめポイントを紹介します。初めて薬膳の資格を検討している方にもわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。
通信教育会社の講座で取れる薬膳資格
1. 薬膳コーディネーター
薬膳の基礎知識を学びたい方に最適です。通信教育大手のユーキャンが提供しており、講座には中医学の基本理論や実践的なレシピ集が含まれています。費用は44,000円で、受講期間は約4ヶ月です。特に、将来的に中・上級者を目指す方には、ステップアップがしやすい点が魅力です。
2. 和漢薬膳師(薬膳マイスター)
日本人の味覚や体質に合わせた薬膳を学べます。講座を提供している「がくぶん」は100年以上の実績があり、受講料は39,900円です。テキストやDVDの内容をオンラインで学習できるため、忙しい方にもおすすめです。
3. 薬膳漢方マイスター
費用を抑えつつスマホで手軽に学びたい方に最適です。月額3,980円のサブスクリプション形式で、最短1ヶ月で資格取得が可能です。初めて利用する場合は特典価格で8,460円から受講できます。
4. 薬膳インストラクター(日本能力開発推進協会認定)
充実したサポート体制が特徴です。手厚い添削指導や就職サポートがあり、受講料は68,800円です。標準学習期間は4ヶ月ですが、700日間の無料サポートが付いているため、自分のペースで学べます。
5. 薬膳インストラクター(日本統合医学協会認定)
統合医療に興味がある方におすすめです。オンラインと紙のテキストで学べるため、学習の進捗を把握しやすいです。受講料は55,000円ですが、キャンペーン中なら21,780円とお得です。
6. 薬膳調整師(+漢方コーディネーター)
漢方の資格も一緒に取りたい方におすすめです。試験免除講座を利用すれば、テストなしで資格を取得できます。受講料は59,800円から79,800円です。
民間スクールで取れる薬膳資格
1. 日本中医食養学会の資格
薬膳アドバイザー、中医薬膳指導員、日本中医薬膳師など、段階的にステップアップできる資格が揃っています。特に日本中医薬膳師は、国際資格である世界中連認可・国際中医薬膳師を受験するための基礎となります。
2. 本草薬膳学院の資格
中医薬膳師コースがあり、中医学の基礎から上級者向けの内容まで学べます。費用は通信・オンラインで16万円強、通学で50万円程度です。
3. 国際薬膳学院の資格
予防医学食養生士、薬膳食療法専門指導士、和学薬膳博士といった資格があり、通学と通信を組み合わせて学ぶスタイルです。費用は初級で13.2万円、中級で25.3万円、上級で29.7万円です。
4. 薬日本堂漢方スクールの資格
漢方養生指導士という資格があり、ベーシックからアドバンス、各種マスターコースまで段階的に学べます。費用はコースによって異なりますが、薬膳マスターまで取得すると30万円程度です。
5. 全日本薬膳食医情報協会の資格
薬膳インストラクターの初級・中級を取得した後、国際薬膳調理師を目指せます。基本的に通学スタイルです。
国際資格
1. 国際薬膳師
中国薬膳研究会(北京)が認定する資格で、本草薬膳学院が提供しています。中医薬膳師コース修了後に受験が可能です。
2. 国際中医薬膳師
世界中医薬学会連合会が認定する資格で、日本中医食養学会の講座を修了後に受験資格が得られます。
3. 国際中医薬膳管理師
世界中医薬学会連合会が認定する資格で、薬膳アカデミアの講座を修了する必要があります。
薬膳の資格は多種多様で、それぞれに特徴があります。あなたの目的や興味に合わせて、最適な資格を選んでみてください。資格を取得することで、健康管理やキャリアアップに大いに役立つでしょう。
漢方アドバイザーは何ができる?
漢方アドバイザーの概要
漢方アドバイザーは、漢方薬の基礎知識や服用方法など、幅広い知識を持つ専門家です。この資格は、一般社団法人日本技能開発協会や東西中医学院、日本チェーンドラッグストア協会などが認定しており、通信講座を通じて取得できます。漢方アドバイザーは、漢方薬局やドラッグストア、健康関連の企業などで活躍することができます。
漢方アドバイザーの主な業務
- 漢方相談
- 漢方アドバイザーは、個々の顧客の症状や体質に基づいて、最適な漢方薬を提案します。これは、詳細なカウンセリングを通じて行われ、顧客の健康状態や生活習慣を深く理解することが求められます。
- 漢方薬の販売とアドバイス
- 漢方薬局やドラッグストアで、顧客に対して漢方薬の選び方や服用方法についてアドバイスを行います。これには、医療用漢方薬と一般用漢方薬の違いを理解し、適切に説明する能力が必要です。
- 健康管理とライフスタイルの提案
- 漢方アドバイザーは、漢方薬の提供だけでなく、食養生や生活習慣の改善など、全体的な健康管理をサポートします。これにより、顧客がより健やかで充実した生活を送るためのアドバイスを提供します。
- 顧客管理
- 継続的なサポートを提供するために、顧客の情報を管理し、定期的にフォローアップを行います。これにより、顧客の健康状態の変化に応じた適切なアドバイスを提供することができます。
- 店舗管理
- 店舗の環境を整え、顧客が快適に利用できるようにすることも漢方アドバイザーの重要な役割です。これには、商品の管理や店舗の清潔さを保つことが含まれます。
漢方アドバイザー資格の取得メリット
- 専門知識の習得
- 漢方アドバイザーの資格を取得することで、漢方薬の基礎知識から応用技術まで幅広く学ぶことができます。これにより、漢方薬を正しく扱い、効果的に利用するための知識が身につきます。
- キャリアアップ
- 漢方アドバイザーの資格は、漢方薬局やドラッグストア、健康関連の企業での就職やキャリアアップに役立ちます。特に、薬剤師がこの資格を取得することで、漢方支援薬剤師としての認定を受けることができ、専門性を高めることができます。
- セルフメディケーションの推進
- 漢方アドバイザーは、セルフメディケーションの推進に貢献します。漢方薬を含めたOTC(一般用)医薬品がより身近なものになる中で、一般生活者や患者に対して漢方薬の知識を伝え、適正使用を促す役割を果たします。
- 自己および家族の健康管理
- 漢方アドバイザーの資格を持つことで、自身や家族の健康管理にも役立てることができます。漢方の知識を活用して、日常の健康維持や病気予防に貢献することができます。
まとめ
漢方アドバイザーは、漢方薬の専門知識を持ち、顧客の健康管理やライフスタイルの改善をサポートする重要な役割を担っています。この資格を取得することで、漢方薬局やドラッグストアでのキャリアアップや、セルフメディケーションの推進に貢献することができます。また、自己および家族の健康管理にも役立つため、幅広い分野で活躍することが期待されます。
薬膳マイスターと薬膳アドバイザーの違いは?
薬膳に興味を持ち、資格取得を目指す方が増えています。その中でも「薬膳マイスター」と「薬膳アドバイザー」という二つの資格が注目されていますが、これらの違いについて詳しく解説します。
薬膳マイスターと薬膳アドバイザーの違い
両者の違いを具体的に見ていきましょう。
-
学べる内容の違い:
- 薬膳マイスター: 日本人向けの和漢膳に特化して学べます。日本人の体質や味覚に合わせた薬膳料理を学びたい方に最適です。具体的には、季節ごとの食材の選び方や、家庭で実践できる薬膳レシピが中心です。また、薬膳の基本理論から応用まで幅広く学べるため、初心者から中級者まで幅広く対応しています。
- 薬膳アドバイザー: 中医学の基本理論や季節ごとの薬膳、食材の効能について学びます。広範な薬膳知識を基礎から身につけたい方に向いています。具体的には、中医学の理論を基にした薬膳の考え方や、基本的な薬膳レシピ、季節や体質に応じた食材の選び方などが含まれます。
-
受講形式の違い:
- 薬膳マイスター: 質問対応や添削指導があり、しっかりとサポートを受けながら学習できます。テキストやDVDを活用して、自分のペースで学べるのが特徴です。また、オンラインでのサポートも充実しており、忙しい方でも学びやすい環境が整っています。
- 薬膳アドバイザー: 課題を提出する形式で、試験がないため、試験のプレッシャーがないのが利点です。DVDやテキストで学び、家庭で実践しやすい内容となっています。講座内容は非常に実践的で、日常生活にすぐに取り入れられる知識が多く含まれています。
-
受講料と期間:
- 薬膳マイスター: 受講料は38,700円、受講期間は約4ヶ月です。短期間で集中して学ぶことができ、教材も充実しています。受講後には修了証が発行され、さらに上級資格を目指すことも可能です。
- 薬膳アドバイザー: 受講料は39,800円、受講期間は約4ヶ月です。こちらも比較的短期間で学ぶことができ、実践的な知識が多く含まれています。修了後には、上位資格へのステップアップも可能です。
どちらを選ぶべきか?
どちらの資格を選ぶかは、あなたの目的によります。
-
薬膳マイスターが向いている人:
- 日本人向けの薬膳料理を学びたい
- 和漢膳に興味がある
- 質問や添削指導を受けながらしっかり学びたい
- 短期間で集中して学びたい
-
薬膳アドバイザーが向いている人:
- 中医学の基本理論から学びたい
- 広範な薬膳知識を基礎から身につけたい
- 試験がなく、課題提出で資格を取得したい
- 実践的な知識をすぐに生活に取り入れたい
具体的な講座内容
薬膳マイスターと薬膳アドバイザーの講座内容について具体的に説明します。
-
薬膳マイスターの講座内容:
- テキスト: 基本的な薬膳理論から応用まで、わかりやすく解説されています。
- DVD: 調理方法や食材の選び方など、視覚的に学べるコンテンツが充実しています。
- レシピ集: 家庭で簡単に作れる薬膳料理のレシピが多数収録されています。
- 質問対応: オンラインでの質問対応が充実しており、学習中の疑問をすぐに解決できます。
- 添削指導: 定期的な添削指導があり、学習の進捗を確認しながら進められます。
-
薬膳アドバイザーの講座内容:
- テキスト: 中医学の基本理論や、季節ごとの食材選び、薬膳の基礎知識を学べます。
- 講義DVD: 調理方法や理論の解説が視覚的に学べるので、理解しやすいです。
- 課題提出: 定期的に課題を提出し、フィードバックを受けながら学習を進めます。
- 質問対応: 学習中の疑問は、メールなどで質問でき、迅速に対応してもらえます。
実際の活用例
資格取得後、薬膳マイスターと薬膳アドバイザーの資格をどのように活用できるか、具体的な例を紹介します。
-
薬膳マイスターの活用例:
- 家庭料理のレベルアップ: 和漢膳の知識を活かし、家庭での食事を健康的でバランスの取れたものにすることができます。
- 料理教室の開設: 資格を活かして薬膳料理教室を開くことができ、健康志向の高い方々に薬膳の魅力を伝えることができます。
- 健康相談: 和漢膳の知識を基に、家族や友人の健康相談に乗ることができ、具体的な食事アドバイスができます。
-
薬膳アドバイザーの活用例:
- 個人の健康管理: 中医学の理論を活かして、自分や家族の健康管理に役立てることができます。
- 職場での活用: 飲食業界や介護施設などで、薬膳の知識を取り入れたメニュー開発や食事指導ができます。
- 資格のステップアップ: 基礎知識をしっかり身につけた上で、さらに上級の薬膳資格を目指すことができます。
まとめ
薬膳マイスターと薬膳アドバイザーは、それぞれに特徴があり、学べる内容や学習スタイルが異なります。自分の興味や学びたい内容に合わせて、適した資格を選びましょう。薬膳の知識を身につけることで、健康的な食生活を実現し、自分や家族の健康維持に役立てることができます。薬膳は日常生活に取り入れやすく、継続することで体調の改善や免疫力の向上が期待できます。
国際薬膳師について
薬膳の資格を取得したいと考える方にとって、どの資格が自分に適しているのか、その難易度や合格率は重要な情報です。特に「国際薬膳師」の資格は難易度が高く、本記事では、国際薬膳師の合格率や資格の詳細について解説します。
国際薬膳師とは?
国際薬膳師は、中国薬膳研究会が認定する薬膳の最高峰の資格です。この資格は、日本では本草薬膳学院が教育機関として認定しており、資格を取得するにはまず中医薬膳師の資格を取得する必要があります。
特徴と取得方法
- 認定団体: 中国薬膳研究会
- 日本の認定団体: 本草薬膳学院
- 難易度: 非常に高い
- 取得方法: 本草薬膳学院で中医薬膳師の資格を取得後、国際薬膳師の試験に合格することが必要です。
国際薬膳師の合格率
国際薬膳師の試験は非常に難易度が高いことで知られています。日本では1999年から試験が実施されており、2021年9月時点で1,490名の合格者がいます。合格率は公開されていませんが、専門的な知識が必要とされる試験であるため、一般的には合格率は50%以下と考えられています。
国際薬膳師の試験内容
国際薬膳師の試験は以下の科目で構成されています:
- 中医基礎学
- 中医内科学
- 弁証施膳
- 中医診断学
- 食材学
- 中薬学
- 方剤学
- 中医営養薬膳学
試験は記述式で、広範な知識と深い理解が求められます。
国際薬膳師を目指すためのステップ
国際薬膳師の資格を取得するためには、次のステップを踏む必要があります:
- 中医薬膳師の資格取得: 本草薬膳学院の中医薬膳師コースを修了し、中医薬膳師の資格を取得します。
- 必要な学習時間の確保: 他の学校や団体で1,000時間以上、中医薬膳学を学んだ証明が必要です。
- 国際薬膳師の試験に合格: 試験に合格することで、国際薬膳師として認定されます。
中医薬膳師コースの概要
本草薬膳学院の中医薬膳師コースは、初めて中医学や薬膳学を学ぶ方向けに設計されています。理論と実習を組み合わせたカリキュラムで、効率的に学習できるのが特徴です。受講形式は通学・通信教育・オンライン(e-ラーニング)から選択できます。
受講期間と受講料
- 通学コース: 1年
- 通信教育コース・オンラインコース: 有効期限2年
- 受講料: 不明(公式サイトで確認が必要)
国際薬膳師の利点
国際薬膳師の資格を取得することで、次のような利点があります:
- 高い信頼性: 国際的に認められた資格であり、薬膳の知識と技術が高く評価されます。
- キャリアアップ: 就職や転職の際に大きなアドバンテージとなります。
- 健康への貢献: 自身や家族の健康管理に薬膳の知識を役立てることができます。
まとめ
国際薬膳師の資格は、薬膳における最高峰の資格として非常に高い評価を受けています。しかし、その取得には多くの時間と努力が必要です。難易度が高く、専門的な知識が求められるため、真剣に学ぶ意志がある方に向いています。薬膳の知識を深め、キャリアアップを目指す方は、ぜひこの資格の取得を目指してみてください。
薬膳漢方検定は難しい?
薬膳・漢方検定は、薬膳や漢方に関する基本的な知識を問う検定試験であり、難易度は比較的低いとされています。以下に、薬膳・漢方検定の詳細と難易度について説明します。
薬膳・漢方検定の概要
薬膳・漢方検定は、薬膳や漢方に関する正しい知識を習得し、日常生活に活かすことを目的とした検定試験です。受験資格に特別な制限はなく、誰でも受験することができます。
試験の詳細
- 出題形式: 4者択一形式
- 試験時間: 60分
- 合格基準: 正答率70%以上
- 受験料: 約6,200円(割引制度あり)
- 試験会場: オンラインで実施
- 実施回数: 年に2回(9月と2月)
出題範囲
試験は薬膳や漢方に関する基本的な知識を問う内容であり、公式テキストを中心に出題されます。公式テキストには、薬膳・漢方の基本知識や身近な食材の効能、薬膳料理のレシピなどが含まれています。
難易度
薬膳・漢方検定の合格率は約90%前後とされており、難易度は低いとされています。これは、試験の内容が基本的な知識に限定されていること、そして公式テキストをしっかりと学習すれば合格できることが理由です。
勉強方法
薬膳・漢方検定の勉強方法としては、以下の点が重要です:
- 公式テキストの熟読: 試験問題は公式テキストから出題されるため、テキストをしっかりと読み込むことが最も重要です。
- 過去問題の解答: 過去問題を解くことで、出題傾向を把握し、試験対策を行うことができます。
- オンライン講座の利用: 必要に応じて、オンライン講座や対策講座を利用することも有効です。
受験者の声
受験者の多くは、公式テキストを中心に学習し、過去問題を解くことで合格を目指しています。試験自体は基本的な知識を問うものであり、しっかりと準備をすれば合格は難しくないとされています。
結論
薬膳・漢方検定は、基本的な知識を問う試験であり、公式テキストをしっかりと学習すれば合格は難しくありません。合格率も高く、難易度は低いとされています。薬膳や漢方に興味がある方にとって、日常生活に役立つ知識を身につける良い機会となるでしょう。
薬膳の資格は意味ない?まとめ
記事のポイントをまとめます。
- 薬膳資格は健康や美容のための知識を得るために有益である
- 資格を取得すると薬膳の専門知識が身につく
- 薬膳資格は国家資格ではなく民間資格である
- 資格取得により日常の食生活に薬膳を取り入れることができる
- 薬膳マイスターは日本人向けの薬膳知識を学べる
- 薬膳コーディネーターは本格的な薬膳レシピを学ぶことができる
- 薬膳資格は通信講座で取得可能である
- 通信講座は自分のペースで学習できる
- 資格取得後は薬膳の知識を活かして仕事に活用できる
- 資格取得は自分や家族の健康管理にも役立つ
- 薬膳資格は趣味としても楽しむことができる
- 資格を通じて薬膳の基礎から応用まで学べる
- 取得期間は4ヶ月程度で、比較的短期間で取得可能
- 資格取得者は薬膳教室やセミナーを開講できる
- 薬膳の知識は飲食業界や美容業界でも活用できる